私は日本史が大好きで、平安末期から鎌倉初期、鎌倉末期から室町初期、戦国時代、江戸時代初期が大変興味を持っています。
これまでこのブログでは、RAPT理論を基に私なりに日本史を推理してきましたが、RAPT理論否定派となった私は日本史に関するブログ記事を一旦ほとんど削除しましたが、これからはRAPT理論の一部を取り入れながら、新たな視点で推理を始めたいと思います。
私はRAPT理論の多くが嘘だと今では考えていますが、日本史については信憑性を感じるものが幾つもあるというのも確かな事実です。
何故ならば、RAPT理論のように戦国時代というのはイエズス会が日本国内で暴れ回っていた時代だと考えると、起きた出来事の内容や経緯が理解しやすいからです。
このブログでも推理しましたように、室町幕府の滅亡、本能寺の変、山崎の戦い、小牧長久手の戦い、千利休の切腹事件、豊臣秀次の切腹事件、朝鮮の役、関ヶ原の戦い、大坂の陣など、RAPT理論を基に推理すると、整合性が取れやすくなるのも確かな事実です。
この点においてはRAPT理論も優秀だと言っておきましょう。
出雲族と秦氏というキーワードで、ある程度日本史の中身を把握できるのも事実だと感じていますので、今後もこのキーワードは利用することになるでしょう。
ただ、鎌倉末期から室町初期にかけては、後醍醐天皇(秦氏)が北条氏(秦氏)を倒そうとしたり、足利尊氏(出雲族)が北条氏(秦氏)を裏切り後醍醐天皇(秦氏)に味方して鎌倉幕府を倒したり、新田義貞(出雲族)は死ぬまで後醍醐天皇(秦氏)に味方したりと、RAPT理論では片づけられない事実もあることから、自ずとRAPT理論には限界が生じているということになり、これだけ取ってもRAPT理論は非真理だと言えるわけです。
真理には限界など生じませんから。
さて、私は織田信長、徳川家康、明智光秀の3人をピックアップしますが、この3人についても、織田信長=秦氏、明智光秀と徳川家康=出雲族なので、すでにRAPT理論が崩れている関係性の一つと言えるでしょう。
おそらく、上級国民は普段の生活において、相手が秦氏だろうが出雲族だろうが余り関係なく、自身の利害関係で動くことが多いのに対して、戦争となると全部では無いにせよ、秦氏側か出雲族側かを重要視するのではないかと私は考えています。
どうしてこの3人に着目しているかと言いますと、この3人は、織田信長が殺される本能寺の変まで、その関係性が維持されているという事実があるからです。
織田信長と徳川家康なんて、戦争の度に連合軍として相手と戦っていますので、このような関係性は戦国時代において、この2人だけだと言っても過言ではありません。
例えば、三国同盟と言われた武田信玄と北条氏康と今川義元の関係は、すぐに崩壊しています。
ちなみに私は、本能寺の変について、その後の歴史的事実を考慮しても、明智光秀の犯行だとはどうしても思えませんので、近いうちに、再び推理を披露しようと考えています。
織田信長と徳川家康が歴史の表舞台に登場するのは桶狭間の戦いの時、明智光秀が歴史の表舞台に登場するのは足利義昭が室町幕府の15代将軍に就任した時になりますが、以前にも書きましたが、私はこの3人は桶狭間の戦い以前から通じていた、と推理しています。
織田信長と徳川家康の関係は、それこそ幼少期から発生しています。
徳川家康は幼少期に、織田信秀(織田信長の父)の人質として2年間、織田家で生活していると伝えられていますが、この時に織田信長と徳川家康の関係は始まっていると私は睨んでいます。
明智光秀については、最近の話において、美濃の斎藤家に奉公していた、と描かれる機会も増えましたが、おそらくは真実だろうと感じています。
明智光秀も斎藤道三の家臣の一人(と言うより軍師)であり、織田信長の正室となる斎藤道三の娘である帰蝶とは、それなりの関係だった可能性があります。
「それなりの関係」とは、男女の仲というよりも明智光秀の片思い的な関係だと推理します。
また、斎藤道三の成功も、軍師的存在無くして有り得なかったと考えられますし、明智家は優秀な人材が豊富にいたと考えていいと思います。
斎藤道三は尾張(織田信長の領地)乗っ取りを企んで、織田信長に帰蝶を嫁がせます(1549年)が、斎藤道三にとっての帰蝶は、それこそダジャレではないですが、帰蝶のためなら死んでもいいと思えるくらい貴重で宝のような存在だった可能性があります。
明智光秀は、帰蝶のボディガード、かつ、斎藤道三の軍師として、帰蝶と共に織田家に派遣されました。
更に、織田信長を見た明智光秀は、一発でその器量を見抜き、敵とするには実に惜しい存在だと考えました。
加えて、織田信長は帰蝶に一目惚れしてしまい、それを上手く利用して、織田信長を味方に取り込み、尾張を支配できるように企んで、斎藤道三に指示を仰ぎます。
ちなみに、織田信長と帰蝶の間には子供が無かった、と言われていますが、嫡男である織田信忠こそ実は帰蝶の子供であり、事情があって生駒家に一時的に預けられていた、と私はとんでもない推理をしていますが、本能寺に織田信長、帰蝶、織田信忠の3人がいたとしても納得感があります。
斎藤道三は「わしと手を組めば、尾張どころか美濃もくれてやると言って懐柔せよ」と明智光秀に指示を出します。
「道三様は信長様に美濃一国をお譲りになる覚悟も辞さないと仰せです。私と手を組んで尾張の支配を固めませんか。」と明智光秀は織田信長に持ち掛けます。
当然ですが織田信長に断る理由などなく、明智光秀は手始めに織田信長の父親の殺害を実行します。
織田信長も何の躊躇もなく父親殺害に同意し、父親である織田信秀を殺害します。(1551年)
時系列からしても、織田信秀の死に斎藤家が関与したとしても辻褄は合うでしょう。
そして続けて、織田信長は自分の守役であった平手政秀を、難癖をつけて自害に追い込みました。
その後、正徳寺で織田信長と斎藤道三は会見を行っていますが、これは両者の綿密な打ち合わせと考えた方が筋が通る気がします。
斎藤道三も織田信長に会って、やはり織田信長の器量を見抜き、明智光秀の報告通りだと認識したのです。
この会見が斎藤道三の命取りとなり、その会見のすぐ後に、長良川の戦いという、斎藤道三と斎藤義龍の親子戦争が勃発し、斎藤家の家臣の多くが斎藤道三ではなく斎藤義龍に従いました。
これは、斎藤義龍が当主であったから、という理由ではなく、織田信長との会見により斎藤道三の策略を斎藤家が知ってしまったことによる斎藤道三潰しだった、と考えた方が納得できると思います。
そうすると戦争するのに十分な理由が出来るでしょう。
斎藤義龍が斎藤道三の実の息子でないために起きた戦争だと通説では説明されることもありますが、それだけでは家臣のほぼ全部が斎藤道三を裏切ったことを説明できません。
斎藤家の家臣からすれば、斎藤道三は美濃を安定させた功労者でもあり実力者でもありますから、そのような事情だけで家臣の全部が戦争まで起こして斎藤道三を裏切るとは考えにくいのです。
斎藤家を揺るがす一大事が起きたために、家臣もみんなが斎藤道三を討とうとした、と考えた方が納得ではありませんか。
斎藤義龍の立場からすれば、いつか父親である斎藤道三に殺されると考えたはずです。
斎藤道三の陰謀を見抜いた斎藤義龍、あるいは、斎藤家の家臣団が、自分たちの利益を守るために斎藤道三を倒そうとした戦争が長良川の戦いだった、という推理はいかがでしょうか。
こうなりますと、美濃の斎藤義龍は尾張の織田信長を倒すために侵攻しそうなものですが、そうならないために明智光秀はしっかりと手を打っていたのです。
美濃には明智光秀の実家である明智家がありました。
当然ですが、斎藤道三のために動いていたわけですが、いざという時、つまり、斎藤道三の陰謀が斎藤義龍に発覚した時には迷わず斎藤義龍側につき、斎藤道三を見捨てるように指示をしていたということです。
織田信長は明智光秀に相当な信頼を寄せていたはずですから、斎藤道三の死により、明智光秀は斎藤道三の軍師から織田信長の軍師になった、と言っていいでしょう。
それ位、この2人はずっと近くで共に行動していますし、織田信長の成功は、イエズス会だけでなく、やはり軍師たる「頭脳」となる存在無くして有り得なかったでしょう。
実際に明智光秀は、織田信長から三千貫もの破格の禄高を貰っていますし、領地として貰った丹波亀山城と坂本城は、安土城の目と鼻の先と言っても過言では無かったわけで、織田信長を警護するには打って付けの場所だったということです。
皆さんも、安土城と亀山城と坂本城の位置関係を調べていただければ、はっきりと分かるでしょう。
このように、織田信長が明智光秀を如何に重要視していたかが分かる証拠を残しているのです。
さて、話を元に戻しますが、斎藤義龍も明智光秀が裏切っていると考えたでしょうが、明智家があっさりと斎藤道三を見限り、明智光秀の尾張潜伏が斎藤家への恭順だったと思わせることが出来、そして、明智光秀も騙されていたと斎藤家を騙すことに成功した、ということです。
加えて明智光秀は斎藤道三に対しても「味方する」と嘘をつき、斎藤道三の援軍と称して織田信長を出陣させたのですが、故意に進軍を遅らせ、斎藤道三を容赦なく見捨てた、ということです。
斎藤道三も、織田信長と明智光秀に裏切られたことを悟り、あっさりと死ぬ道を選んだというわけです。
明智光秀は、斎藤道三の指示に従う裏側で、斎藤家に陰謀が発覚した時の手を抜かり無く打っていたということです。
そのためにも織田信長に力を付けてもらう必要があったというわけです。
これにより、斎藤義龍による尾張侵攻も防ぐことに成功できたということですが、織田信長と明智光秀はこの時に美濃を自力で手に入れなければならない状況になってしまった、というわけです。
斎藤道三を失った織田信長と明智光秀は、尾張統一に向けて急ぐ必要が出てきました。
そこで、時系列は前後するかもしれませんが、織田信長は親族の織田信友を殺し、叔父の織田信光を殺し、最大の強敵であった弟の織田信勝を殺して、身内で力を持っていそうな人物たちをことごとく消し去ったのです。
弟の織田信勝との争いは家臣を巻き込むほどに大きかったのですが、織田家の重臣達は最終的に織田信勝を裏切りましたので、織田信長と明智光秀の強さに圧倒されたということでしょう。
そして織田信長は尾張の支配が固まったことにより、次の手を打ちます。
そうです、桶狭間の戦いです。
これは、今川義元が調子に乗った織田家を討伐するために戦争を仕掛けた、と言うよりも、今川義元を倒すために織田信長が仕掛けた戦争だと私は考えています。
そこで徳川家康の存在が重要になって来るのです。
織田信長は、幼少期に付き合いのあった徳川家康(当時は松平元康)に目を付けたわけです。
おそらく、織田信長と徳川家康との間には、幼少期に結ばれた約束があった可能性もあります。
当時の織田信長は現代で言えば中学生で、徳川家康は小学校低学年でした。
織田信長は「俺が尾張を支配した時には俺が今川を潰してやる。その暁にはお前に駿河の支配を任せるから、それまではどっぷりと今川の人間となり欺き通せ」と言って、人質交換の際に送り出した、という私の推理です。
そんな子供の時の約束を真に受ける奴がいるのか、と指摘を受けそうですが、織田信長はその時の約束を果たすかのように徳川家康に対して振舞ったわけです。
おそらくは、明智光秀も織田信長から徳川家康の存在を耳にしていて、今川家にも明智光秀は調略の手を伸ばした可能性もあります。
何せ、桶狭間の戦いの数年前、太原崇孚雪斎(たいげんそうふせっさい)という今川義元の軍師が死んでいて、これにより今川家の戦力は大きく削がれてしまうのです。(1555年)
話が元に戻ってしまいますが、長良川の戦いは1556年でしたので、本来ならば斎藤道三に尾張にいた反信長勢力を滅ぼしてもらい、その間に今川を潰すという計画も、もしかしたらあったかもしれません。
私は、雪斎さえも織田信長と明智光秀によって暗殺されたと推理します。
この実行犯が徳川家康だった、というのはとんでも無い推理でしょうか。
雪斎は無類の酒好きだったようで、それを利用されて殺された可能性があります。
徳川家康は常に雪斎の傍で学んでいたようですから、毒を盛るには好都合だったわけです。
徳川家康は、織田家の人質から今川家の人質になり、桶狭間の戦いでは今川軍として戦争をしています。
ちなみに徳川家康は今川家の人質生活の時に、今川義元の姪である瀬名を正室として娶っています。
そうすることで、徳川家康は今川家の親戚となり、今川義元から絶大の信頼を得ることに成功し、調略は着々と進んでいたのです。
実際に徳川家康は、今川義元が桶狭間の戦いで死ぬと、その正室とは別居したわけですが、これだけでも不自然さが際立っていますし、後々、瀬名の子供で嫡男の徳川信康を、家康は瀬名と共に殺しています。
織田信長と明智光秀にとって、機が熟したとでも言いますか、尾張支配の完成、今川家の軍師暗殺、美濃への懸念皆無、と戦争するには十分な条件を揃えたと言えるでしょう。
織田信長は今川義元を挑発したものと思われます。
現代でも、強い相手が弱い相手に馬鹿にされると、強い相手は十中八九怒るじゃないですか。
分かり易く例えるならば、大人が小学生からからかわれたらカチンと来るでしょう。
「このクソガキが!!」と、行動で殴るまではしなくても感情では怒るでしょう。
今川義元は織田信長の挑発にまんまと嵌り戦争を決断したのでしょう。
織田信長は明智光秀を通して、徳川家康に今川軍の先陣を務めるように指示し、囮(おとり)として作った砦の城を攻撃するように指示し、そうすることで内通を見破られにくくしたということです。
徳川家康の先陣の申し出に今川義元は大喜びしたことでしょうし、今川義元を唆すことに成功したのです。
徳川家康が攻めて来た時に、織田家の誰かと徳川家(当時は松平家)の誰かが密会したと考えても不自然さは無いでしょう。
今川義元の居場所を特定できるように画策した、ということです。
と言いますか、間違いなく今川義元が桶狭間という場所で休息を取る、あるいは、宴会を催すように織田家の誰かが唆しているはずです。
今川義元は織田信長を相手に、相当な余裕と油断が生じていたのは間違いないでしょう。
織田信長は、そこを上手く利用したというわけです。
本当に徳川家康が今川義元の家臣として先陣を務めたのならば、途中で織田家への攻撃をやめていることこそ不自然なわけです。
だって、徳川家康はことごとく織田家の砦の城を打ち破っているわけですから、どんどん攻撃しないのはおかしいでしょう。
むしろ、一気に片を付ける絶好の機会だったはずです。
それだけでも、織田信長と徳川家康が通じていたと断じてもいい位です。
加えて、織田信長の重臣であった佐久間盛重が死ぬほどの激戦だったと言われていますから、やはり今川方の勝利は目前だったと言えるのではないでしょうか。
そのような大優勢の中で攻撃の手を緩めるなんて有り得ないでしょう。
まあ私としては、織田信長は佐久間盛重をも捨て石として使った、と考えています。
このように桶狭間の戦いは、何も奇跡的な戦争ではなく、どこまでも初手から織田信長と明智光秀の調略による勝ちが確信できていた戦争だったということです。
よくドラマで描かれていますが、織田信長が帰蝶の前で、桶狭間の戦いの出陣直前に敦盛を舞っていますが、戦勝祝いをしていたとしか思えません。(笑)
それ位、織田信長は今川義元に勝つ自信があったということでしょう。
要するに、徳川家康にとって織田信長と明智光秀は大恩人ということになり、この三者が本能寺の変までその関係性が崩れることなく維持できたのは、桶狭間の戦いとそれ以前に全てがある、というのが私の推理になります。
そして織田信長はイエズス会と出会い、資金支援を受けることになるのですが、そのことが織田信長の人生だけでなく、明智光秀の人生も徳川家康の人生をも狂わすことになるのです。
ちなみに、2020年NHK大河ドラマの「麒麟がくる」は、明智光秀を主人公として描いていますが、斎藤家で重要視されていたことや織田信長との関係も、それまでには無い視点で結構深く描かれていますので、真実ではないけれども真実に少しでも近いように描かれていた、というのが私の印象です。

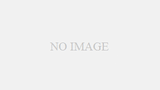
コメント