今回は、いよいよ本能寺の変の真相に迫りますが、「ああでもないこうでもない」と考えていましたので、記事の更新が少々遅れました。
1582年5月、安土城にいた織田信長に豊臣秀吉から一通の手紙が到着します。
「戦況は非常にまずいです。このままでは私の軍勢は毛利氏に敗れてしまいます。一刻も早く中国地方への援軍要請を願います。」というものでした。
言うまでも無く、これは豊臣秀吉の織田信長を暗殺するための、誘い出す策略でした。
当然、そのような陰謀があるとは少しも疑っていない織田信長は、安土城にて綿密な軍議を開くことを決め、徳川家康に対して主だった重臣を引き連れて安土城に来るように指示を出しました。
これが、世に言う「徳川家康接待」の真実です。
申し訳ないですが、武田家滅亡の戦勝祝いの接待なんて有り得ない話であり、戦争するための軍議だったと考えた方が、どう考えても整合性が取れるでしょう。
徳川家康も重要な戦争だと重々分かっていましたので、織田信長の指示に従い、主だった重臣と共に軍勢を率いて安土城に入城したのです。
いいですか、皆さん。
時代は戦国時代真っ只中です。
織田信長にとっても、まだまだ周囲は敵だらけといった情勢です。
いつ命を取られるかも分からない情勢の中で、徳川家康が数人の重臣たちだけで安土城に赴くなんて有り得ると思いますか。
そのような情勢の中で、悠々とのこのこと、お遊び気分で宴会を開いている余裕など、どこにもないことは誰が考えても明らかでしょう。
しかも、駿府から安土まで、どれほどの距離があると思いますか。
現代でも車を使用して数時間かかるレベルなのに、あんな接待の話、どこまでも現代の感覚、もしくは、戦争の心配が無い時代の感覚ですよ。
話を戻します。
通説では、豊臣秀吉は毛利氏との戦争にかなり苦労していたように言われていますが、そうではなく、織田信長暗殺の機会をひたすら伺い、そのための時間稼ぎをし、茶番劇とも言える毛利氏との戦争をしていたに過ぎず、武田氏を滅ぼすことに成功したという知らせを受けて機が熟したと見て、豊臣秀吉がイエズス会と毛利氏と結託して暗殺計画を練っていた、ということです。
軍議には織田信長と徳川家康を始め、織田信忠、明智光秀、丹羽長秀などが出席しましたが、実はこの時に既に丹羽長秀は豊臣秀吉と通じていた、と私は睨んでいます。
更に実は、その軍議の最中に、もう一つの罠が仕掛けられていました。
千利休からの茶会の誘いでした。
実は1996年のNHK大河ドラマ「秀吉」では、私の記憶違いで無ければ、千利休は安土城あるいは本能寺にいた、という設定になっています。
千利休は、間違いなくイエズス会と通じていた人物で、スパイ役と言っても過言では無く、イエズス会は彼に堺の町を牛耳らせていました。
実際に当時の戦国武将たちも千利休を慕って、次々とキリシタンとなる大名たちも現われ、イエズス会に同調する動きが盛んに行われていたことを鑑みますと、千利休がイエズス会の回し者であった可能性は非常に高いと考えられるわけです。
千利休は当時、安土城に招かれていた可能性が高く、織田信長と徳川家康と明智光秀の軍議の様子を知っていた可能性も十分あるでしょう。
何せ、千利休は織田信長の茶頭(さどう)を務めていたからです。
イエズス会にとって、裏切り者の織田信長を殺すためには、千利休の存在や寝返り者の存在は欠かさせなかったわけで、織田信長裏切り後も千利休を織田信長の傍に付けていた、ということです。
ちなみに、陰謀の秘密を知っていた丹羽長秀は元々は織田信長の重臣であったため、再び織田方に寝返る可能性も否定できず、本能寺の変の後、豊臣秀吉によって口封じのため殺された、という私の推理です。
イエズス会は織田信長の茶道への異常な執着を利用しようとして千利休を近づけていたのです。
千利休は「中国への出陣の前に、京の本能寺にて茶会を催し、そこで信長様が欲している名器を餞別代りに差し上げましょう。」と織田信長を本能寺に誘い、織田信長も喜んで応じました。
そこで織田信長は、織田信忠、徳川家康、明智光秀に本能寺で合流することを伝えました。
明智光秀は本能寺での茶会には大反対でした。
そこで自分の居城に戻る前に、織田信長と2人きりで面談をします。
「千利休は油断ならない奴です。あれはイエズス会と通じていても何らおかしくはありません。茶会には絶対に行ってはなりません。茶器は別の機会にでも譲り受けて下さい。」
明智光秀も茶道に関しては織田信長ほどで無いにせよ嗜んでいましたが、明智光秀にとっては千利休を探るための作戦の一つだった可能性もあります。
この当時における茶道は、戦国大名にとっては一つのステータスだったでしょう。
よもや反対されると思っていなかった織田信長は、思わず明智光秀を殴ってしまうのです。
それ位に織田信長の茶道に対する執着、特に茶器に対する執着は尋常ではなく、明智光秀は一抹の不安を抱えました。
「ならばせめて、上様(織田信長)の警護として、私も本能寺へ同行させて下さい。」と明智光秀は懇願しますが、「光秀、お前はどうかしている。あのような場で奇襲を起こせる者どもがいるはずがない。まあお前がそこまで言うなら、万が一に備えて警護には腕の立つ森蘭丸以下しっかりと準備しておく。お前は予定通り軍勢を引き連れて6月3日の早朝には本能寺へ着くように出陣の支度をせよ。」と織田信長は指示します。
私の推理では、茶会の場での奇襲などは大それた粗相という認識感があり、武将として恥ずべき行為だったため、茶会の場で奇襲攻撃を受けるという考え自体が織田信長には無かった、と考えるとどうでしょうか。
そう考えますと、暗殺の成功率は100%に限りなく近づくと思います。
それでも不安を拭い切れない明智光秀は、万が一に備えるべく、織田信長の警護を固めるために織田信忠には本能寺に近い妙覚寺で待機するように指示し、徳川家康は千利休の本拠とも言える堺で待機するように指示しました。
明智光秀は胸騒ぎがしてならなかったのですが、織田信長の指示に従い出陣しました。
明智光秀は本能寺へ向かう道中で愛宕神社に参拝し、戦勝と織田信長の無事を祈願したのです。
一方で豊臣秀吉は、千利休から「織田信長は6月2日、京の本能寺で茶会を催すので、その場で暗殺を実行する」と報告を受けました。
備中高松城にいた豊臣秀吉は、織田信長暗殺の成功を確信(織田信長を茶会と称して本能寺に誘い出すことに成功した時点で、豊臣秀吉やイエズス会側にとって暗殺成功が約束されたも同然だったのです。)していて、京へ向かうには都合の良い姫路城を選び、毛利氏からも援軍を預かり大軍を率いて、待機して知らせを待つことにしました。
実際にNHK大河ドラマ「秀吉」でも、私の記憶違いで無ければ、豊臣秀吉が中国大返しの最中に姫路城に寄っているシーンが描かれていますので、私が推測するに真実だろうと思うわけです。
世に言う「中国大返し」は真っ赤な偽りであり、豊臣秀吉は、いつでも織田軍、いや、明智光秀を倒すために用意万端整えていた、ということです。
そして6月2日を迎えます。
織田信長と織田信忠は、護衛兵(以下「SP衆」と表現します)と徳川家康の軍勢に守られながら、それぞれ本能寺と妙覚寺に入ります。
本能寺で行われた茶会には、織田信長の妻である帰蝶も同席し、織田信忠も同席しましたが、織田信忠の同席については、家臣以外誰も知らされていませんでした。
父である織田信長から「お前も来い。」と誘いを受けていたかもしれませんし、千利休から誘いを受けていたかもしれません。
織田信長のSP衆も僅かな人数だったわけで、このように考えれば、織田信長が僅かな人数で本能寺に入ったのも説明が付くでしょう。
茶会の場においては、それ相応の茶人たちも招かれていたでしょうから、その護衛のためにSPが何人も付けられていた可能性は大いに考えられ、そのSPこそが刺客だったという推理です。
茶会も終わりを迎えた時、茶人のSPの一人(あるいは茶人に扮した刺客)が千利休から預かったという茶器を織田信長に渡そうとしたその時、懐に収めていた短刀で織田信長の心臓を一突きしたのです。
即死でした。
織田信長への攻撃が奇襲の号令となり、茶人のSP衆が織田のSP衆に襲い掛かり、次々と殺されていきました。
織田信忠も帰蝶も殺されてしまいました。
茶人のSP衆は本能寺に火を放ち、遺体もろとも焼き尽くそうとした上で、更に陰謀を実行します。
つまり、今度は妙覚寺に向かい、織田信忠の家臣達を襲い皆殺しにした上で、妙覚寺にも火をつけて逃走しました。
本能寺周辺の上空が明るいのに気付いた明智光秀は、思った通り奇襲が起きたと悟り、急いで本能寺へ駆けつけました。
しかしながら、時既に遅く、妙覚寺にも火の手が上がっているのを確認した明智光秀は、万事休すと悟ったのです。
織田信長、帰蝶、織田信忠の遺体は焼失してしまいました。
実は、妙覚寺にいた織田信忠の護衛兵も軍勢と言うには程遠く、刺客にあっさりと打たれてしまったということです。
つまり、今回の織田信長の中国地方遠征の軍勢の大半は、明智光秀と徳川家康の軍勢だった、と考えれられます。
おそらく徳川家康軍も多くても数千位であり、明智光秀の軍勢が主だった可能性は大いに考えられます。
これが私の推理する織田信長の死の真相です。
本能寺における織田信長暗殺は、イエズス会側にとって、失敗の許されない極めて重要な陰謀だったので、茶会という高貴な場を利用したということです。
絶望感しかなかった明智光秀ですが、直ちに堺にいた徳川家康の元へ行き事態の急変を告げ、駿府へ急いで戻るように指示しました。
世に言う、徳川家康の死に物狂いの「伊賀越え」は、そういう意味では真実だと考えています。
織田信長暗殺成功の知らせを受けた豊臣秀吉は、直ちに姫路から出陣します。
織田信長と織田信忠を同時に失った明智軍と徳川軍が動揺しないはずも無く、逃げるので精一杯でした。
明智光秀はまだこの時点では、豊臣秀吉が裏切っているとは少しも思わず、京周辺にいた織田信長の家臣達を集結させようとしますが、娘の嫁ぎ先である細川藤孝忠興親子さえも取り込まれていたほどにイエズス会の根回しは進んでいて、実はこれも豊臣秀吉の巧みな工作でした。
豊臣秀吉は織田信長暗殺が成功する前から「織田信長は明智光秀の裏切りにより死んだ」という虚偽の報告を6月3日には織田信長の家臣達に届けるよう、伝令に指示していたのです。
「明智光秀による謀反」というシナリオが当時に出来上がっていた、ということです。
この報告を、織田信長の家臣達の多くが真に受けました。
ちなみに、細川藤孝は織田信長の命により、嫡男の細川忠興に明智光秀の娘である玉を嫁がせていました。
細川藤孝は足利義昭の家臣だった人物でしたので、織田信長にとっては家臣にしたものの信用できる相手ではなく、よって明智光秀と親戚になるように計らい、牽制したわけです。
細川藤孝も元々は足利義昭の家臣であったため、織田信長や明智光秀のことは良く思っていなかった可能性も高く、しかもその足利義昭は毛利氏の庇護の下にいたとなれば、豊臣秀吉に味方する理由は大いにあったというわけです。
玉とは後の細川ガラシャですが、本能寺の変の直後、細川藤孝は玉を殺すように息子の忠興に指示をしましたが、玉にぞっこんだった細川忠興は、殺すことが出来ず幽閉するのが精一杯でした。
玉の幽閉が解かれたのも、キリシタン(イエズス会の仲間)となったからでしょう。
本能寺の変の直後、豊臣秀吉に味方した織田信長の家臣達の多くが、途中から織田信長の家臣となった連中でした。
織田信長と明智光秀に対して、心から従っていたわけでは無かったのでしょう。
周辺の味方たちから裏切られた明智光秀は、朝廷の力を借りて戦争を一時的にでも止めてもらうなど、何とか事態の改善に向けて力を尽くしていました。
そのような最中、明智光秀にとんでもない寝耳に水のような報告がもたらされます。
「豊臣秀吉が大軍を率いて目前に迫っています。」
イエズス会の犯行だとは思っても豊臣秀吉の犯行とは考えていなかった明智光秀は、全てが豊臣秀吉の裏切りによる陰謀だとすぐに悟りました。
毛利氏との戦争の最中である豊臣秀吉が京に迫っていることは有り得ない事実であったため、明智光秀もすぐに理解できたわけです。
明智光秀は完全に嵌められたわけですが、明智光秀の裏切りを信じなかったのが、柴田勝家であり、市であり、滝川一益であり、そういった織田信長の古くからの重臣や身内のみであり、だから最後まで豊臣秀吉に敵対したわけです。
明智光秀は豊臣秀吉との戦争を覚悟します。
豊臣秀吉の予想だにしない行動に、明智光秀は死を覚悟して豊臣秀吉との戦争に臨むほかなかったのです。
その際に実は、明智光秀は自分の従弟である明智秀満に全てを託していたのです。
通説では、明智秀満は明智光秀の重臣と言われていますが、やはりただの重臣と言うだけでは明智姓は名乗れないと思いますので、やはり身内と考えていいでしょう。
明智秀満も明智光秀のように非常に優秀な人物でした。
「俺はこの地で死ぬが、お前は直ちに徳川様の元へ行って仕えよ。棟梁無き織田家を救えるのは徳川家康しかいない。いつか信長様と私の無念を晴らすべく、徳川家康と協力して豊臣秀吉を滅ぼすべし。」と命令して、明智秀満と主だった身内には参戦させませんでした。
明智光秀の重臣であった斎藤利三も、徳川家康を頼ろうとしたのですが、妻が実家へ戻りたいと強く要望したため、妻の実家である稲葉一鉄に、妻と娘である福(後の春日局)を委ねました。
始めから勝ち目が無いと考えた明智光秀は、必要最小限の軍勢に留めて、全てを明智秀満に渡したのでした。
この明智秀満が後の南光坊天海であり、また明智光秀の重臣だった斎藤利三の娘である福は春日局として江戸城大奥で権勢を振るう人生を送り、いずれも明智光秀一族が徳川家で栄華を極めることになるのです。
こんな偶然は絶対に有り得ません。
更には、徳川家康は江戸幕府2代将軍の徳川秀忠には、織田信長の姪である江を嫁がせていますが、徳川家に織田家の血も入れていたということです。
話を元に戻します。
山崎の戦いは、明智光秀の惨敗に終わりました。
明智光秀の死は、逃げ延びる途中で落ち武者狩りに殺された、と伝えられていますが、私はこれも後世の創作、いや、豊臣秀吉の創作だと考えています。
武将にとって落ち武者狩りで殺されたとなれば、何とも屈辱的でみっともない最期、と印象付けることが出来ます。
一方で戦場での死は、武将にとっては誇りある死となるはずです。
明智光秀は自身の最期が迫っていると悟ると、「信長様、帰蝶様、信忠様、間もなく私もそちらへ向かいます。守り切れなかった私をどうかお許し下さい。ただ対面の折は私を激しく叱責して下さいませ。」と語り、壮絶な死を遂げました。
明智光秀の首とその重臣であった斎藤利三の首は、後日、三条河原に晒されました。
豊臣秀吉は織田信長だけでなく明智光秀のことも憎らしく思っていて妬んでいたのでしょう。
だから豊臣秀吉は、「惟任退治記」と称する本を大村由己(ゆうこ)に書かせて、如何にも明智光秀を蔑むかのような名称で編纂させたのでしょう。
ちなみに、山崎の戦いの後に行われた清須会議も、全くの嘘でしょう。
いいですか、皆さん。
清須会議の場に出席したと言われているのが、柴田勝家、豊臣秀吉、丹羽長秀、池田恒興、滝川一益です。
ドラマによっては前田利家がいたりもしますね。(笑)
遠征に赴いているはずの織田家の重臣たちが、のこのこと織田家相続の会議で集まる余裕なんてあると思いますか。
織田信長の死が知られれば、それこそ敵から猛攻撃を受ける羽目になるはずです。
「清州で織田家家督相続のための会議をするから一旦休戦してほしい」と依頼したとして、相手(敵)が停戦や休戦を承知するとでも思いますか。
そのような情勢の中で、戦争の指揮官(総大将)が現場を離れるなんてこと、有り得るとでも思いますか。
主君から呼び出しを受けるのならばいざ知らず、事態は主君を失っているわけです。
考えられるのは、せいぜい、豊臣秀吉と市と織田信雄と織田信孝の4者会談くらいなものでしょうが、織田信長を失った織田家の人達に、豊臣秀吉と会談できる肝の据わった人間は果たしていたでしょうか。
父親が殺されているのに、殺した相手と面会するなんて殺されに行くようなものです。
つまり、織田家の家督相続を三法師に決めたのは、豊臣秀吉が自分勝手に決めたことによる独断と偏見だった、と考えた方が筋が通るでしょう。
太閤記なんて出鱈目もいいところだと言っておきましょう。
以上のように豊臣秀吉は、明智光秀が謀反を起こしたかのように見せかける工作づくりも巧みに行っていた、ということです。
本能寺や妙覚寺を焼き払ったのはその典型ですね。
ということで、本能寺の変の真相を推理してみました。
またまたそう言えば、NHK大河ドラマ「秀吉」では、本能寺の変が起きる直前まで石田三成が織田信長の傍にいた設定になっていますが、当時の私は有り得ないと思いながら見ていましたが、現在の私の推理からすれば、十分に有り得る話だと言えます。
当然ですが、素人が推理していますから、穴があるのは仕方がないとご容赦ください。
ただ、指摘された穴についても、なるべく答えられるように準備したいと思っています。
もしも「これはどうなんだ」というようなご指摘があれば、是非コメント欄にてご指摘いただけると有難く思います。
イエズス会と毛利氏の力によって、やがて天下統一を果たす豊臣秀吉も、織田信長のようにイエズス会を裏切る日がやって来て、織田信長と同じような運命を辿ることになるのです。
そうです、豊臣秀吉も暗殺され、彼の死により関ヶ原の戦いという、天下分け目の秦氏対出雲族の全面戦争へと突入していくのです。
毛利輝元が西軍(秦氏)の総大将に任命されたことが、イエズス会の陰謀(日本の頂点に毛利氏を据える)があったことを示す何よりもの証拠と考えています。
そう言えば、1992年のNHK大河ドラマ「信長」では、イエズス会の視点から、ルイスフロイスを語り手として描いていましたが、あれはやはり、庶民を真実から遠ざけるためのドラマと考えていいでしょう。
いつの日か、私の推理が世の中に採用されて、NHK大河ドラマの監修など手掛けることが出来れば最高の人生となるでしょうが、まあまず実現不可能な大それた私の儚い夢です。(笑)
また、近いうちに豊臣秀吉時代に起きた様々な出来事の推理を披露したいと思います。

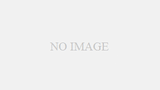
コメント